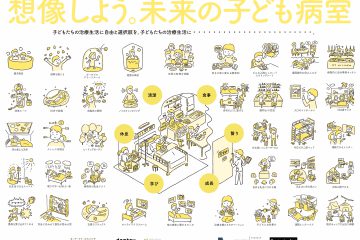今のままで、できることはいっぱいある –ダイアログ・イン・サイレンス、その先に思い描く未来

- 共同執筆
- ココカラー編集部
20日間で当初予想を超える3,500人を導入したダイアログ・イン・サイレンス。総合プロデューサの、志村季世恵さん(一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ)にお話を伺いました。
ダークから、サイレンスへ
編集部: 視覚障害者にアテンドされ暗闇を探求するソーシャル・エンターテインメント「ダイアログ・イン・ザ・ダーク(以降ダーク)」を1999年から日本で開催されていらっしゃいますね。今回、ダイアログ・イン・サイレンス(以降サイレンス)を開催しようと思ったきっかけはなんですか?
志村: 最初にサイレンスの話を聞いたのは、今から22年ほど前のことでした。発案者のアンドレアス・ハイネッケ博士は、ダーク開催直後からサイレンスの構想も持っていたのです。話を聞いた時から私たちもいつか日本でもやりたいと思っていました。私には何人かの「耳の聞こえない」友達がいますが、人の動きや表情を読み取る力が非常に長けています。また表現力も素晴らしいのです。この人たちの持つ文化を知ることができたら、日本はもっと豊かな国になるのではないかと思っていました。

編集部: 実際の開催にあたり、どのように展開を考えていったのですか?
志村: 私自身がもっと耳の聞こえない人たちの世界を理解することが大切だと思い、松森果林さん(聞こえる世界と聞こえない世界をつなぐユニバーサルデザインアドバイザー)に相談しました。松森さんとご一緒にサイレンスを開催したいと願っていたこともあったからなのですが、ただ私は手話ができないので、このまま進めるのは難しい。先ずは手話を学ばなければと感じていたのですね。けれど東京オリンピックの開催が決まって、「これは、ゆっくりはしていられない。ここで本当にがんばらなければダメだ」と拍車がかかりました。
編集部: サイレンスの日本開催に関しては、発案者のハイネッケ博士から、意外な反応があったと伺いました。
志村: 開催許可をくださいとお願いしたら「もともと静かで表情を出さないことをよしとしている日本の人たちが、敢えてそんなことをしなくていいんじゃないか」って言われたんですね。予想外の返事に驚きましたが、感情を顔に出して伝え合うことをあまりしない日本でサイレンスを開催して成功するのか心配だったのではないかと思います。その後何度かやり取りしていましたが、ある日ハイネッケ博士が「能の世界と思えばいいのか」と言ったんです。能はたった4つのお面ですべてのことが演じられるようになっていますよね。それも、表情が変わらないにも関わらず、俯き加減だとか、影とかで、喜怒哀楽を見せていく。そこから「日本人は美学をもって伝えている」と日本人の表現を捉え直してくれて、開催許可が降りました。去年の今頃のことでした。

 (イスラエルチームとの事前研修。異なる言語、異なる手話を超えてつながりあった)
(イスラエルチームとの事前研修。異なる言語、異なる手話を超えてつながりあった)
日本人の感受性に合わせたアレンジ
編集部: 日本向けに、内容をアレンジした部分はあるのですか?
志村: はい。しています。ヘッドセットを外し手話通訳の方を介しアテンドと対話をする部屋があります。海外の開催国はこの部屋を最後としてサイレンスの体験は終わります。しかし日本の場合はもう一つ部屋を加えました。理由は海外の人の反応と、日本人の反応は違うだろうと予測していたからです。外国人はディスカッションが得意で、体験後に余韻を味わうより言葉にすることを好みます。しかし日本人は言語化するより余韻に浸る時間を必要とする。それから言語化するのですよね。日本人は非常に感性が豊かなのだと私は思っています。そこで少しゆとりあるコンテンツとして新たな部屋を加えました。アテンドと共に様々な部屋を巡り楽しんだ時間。そして手話通訳士を介して対話する部屋。最後は、この体験は一体なんであったのかを考える時間を持つという部屋です。この類い稀な経験をご自身の何らかの発見や、実社会に反映するために使っていただきたいという思いからアレンジした部屋でした。
 (ダイアログ・イン・サイレンス 通訳と話す部屋)
(ダイアログ・イン・サイレンス 通訳と話す部屋)
編集部: 日本人の感受性に合ったプロセスを大切にしているのですね。
志村:海外では学校教育の一環として、ダイアログ・イン・ザ・ダークやサイレンスの体験が入っています。いづれもエンターテインメントとして楽しみながら何かを学ぶことができます。また街の中には障害者が多く出歩いていて交流する機会も多いのです。でも日本では、交流の場ってあんまりないんですね。あるとしても福祉的な形で障害者は大変で助けてあげなければならない可哀想な人として出会わせてしまう場合もあるように感じています。でも私たちは「障害の大変さを理解しましょう」というのではなく、「互いの強みや言い分を知っていきながら出会う」のが大事だなって思っています。どんな人も、ものすごく素晴らしいものを持っているし、どんな状況も、考え方ひとつで変わるんじゃないかってことを知って欲しいんですね。そして、誰もが本当に助け合い、生かし合う場を体験してもらえたらって願っています。
編集部: 「見えない人」と「聞こえない人」が交流することもあるのですか?
志村: 日本では、ダークのアテンドが、研修の講師役として登場し、アテンドの先輩としてその醍醐味や注意点なども伝えていました。これを発案者に伝えると驚いていました。聞こえない人に対し、見えない人が伝えるということはなかなか容易ではないのです。一方からすると表情が見えないので手応えがないですし、もう一方からすれば音声として耳に入ってこない。やはり手応えが感じられない。でもそれを越えようとみんなで工夫し努力します。もちろん手話通訳士が間に入ってくれてはいるのですが、それだけだと直接的な交流がないので、最後には身体表現を使って、みんなでダンスをしたんです。手話でも音声言語でもなく身体で表現していくと、混ざり合っていくんですよ。不思議な一体感を得ることが出来ました。努力すれば通じることも分かりました。そして飲み会もしました。実際にサイレンスに全盲の方がお客様としてご参加くださいましたが、この研修もあったことでよい状態でご対応もできていたように思います。
ダークとサイレンスの違いと多様な可能性
編集部: ダークも体験したことのある方から、「サイレンスには見続ける緊張感があった」という感想を伺いました。それぞれの体験から得られる気づきの違いをどう感じていますか?
志村: 確かに相手を見続けるってあまり経験しないですものね。ただダークもサイレンスも、ご体験者が何を感じ何をお持ち帰りなさるのかはその人によって違うようです。ある日、外国人と、難聴の人と、健聴者が混ざっている回がありました。まさにダイバーシティという感じでしたが、その回にご参加くださった若い女性が「世界はひとつだったと思った」と仰っていました。その方は人と関わることが苦手で中学・高校と学校に行けなかったそうなのですが、言葉がなくても、知らない国の人とも通じ合える、本当はとても簡単なことだったのだとすごく感動したんですって。するとアテンドがその方に「私も聞こえなくなった時に学校に行くのが嫌になったことがありました。友達がいなかったからです。でも、自分ひとりの時間を持つことも大事と本を読んだりしていました」と伝えたら、その方は「考え方一つで、物事って違うんですね」と仰っていました。とても明るい笑顔でした。
 (研修後の集合写真。イスラエルチーム、発案者のアンドレアス・ハイネッケ博士らと共に)
(研修後の集合写真。イスラエルチーム、発案者のアンドレアス・ハイネッケ博士らと共に)
志村: 実は私も、アテンドに大切なことを教わりました。それは耳が遠くなってきた私の母のことを話したことがきっかけだったのです。母は補聴器を使いたがらないので、話しかけるときは声を大きくしないといけません。優しい声では聞こえないので、私も必死。するとその声は怒っていると感じてしまう。最近は「おはよう!」の挨拶も聞こえていないようで、母は挨拶もせず自分を無視しているとまで思っている。このようなことをアテンドに相談したことがありました。すると「話しかける前にお母さんの肩をとんとんと叩いてみたらどう?」ってアドバイスをもらったのです。それ聞いたら、涙がでてきちゃったんですね。私は声を介したコミュニケーションだけをとろうとしていたのです。「とんとん」のあとに笑顔で伝えるとか、表情で伝えるとか。ボディで伝えるとか、いろいろあっていいことを、私自身が教わりました。やはりアテンドの知恵だと思うのです。本人からすれば当然のことかもしれません。けれど健聴者にはその知恵はありません。私に至っては工夫すら思いつきませんでした。アテンドとの出会いによって大切なことを知ることができる。できないのは、「気持ちがない」わけではなくて、「知らない」からなんですよね。だから、どうしたらいいか、知れることがとても大事。ダークもサイレンスも、ウィズ・タイム(「知恵ある人々との対話」。70歳以上の高齢者のファシリテーターの案内による対話型エンターテインメント)も、アテンドとの出会によって新たなことを知ることができる。お説教でもなく、訴えでもなく、楽しみながら感じていけるのっていいなあって思います。
編集部:今後企業がサイレンスを日本で導入するとしたら、どんな使い方が考えられるでしょう?
志村: 伝えること。聞くこと。分かりあうために努力すること。これはビジネスにおいて重要なことです。それを習得するためにサイレンスを導入することは最適だと感じています。表情も豊かになりますから、相手に気持ちを伝えるときに表情も加われば更に伝わりやすいですよね。最近よく耳にすることですが、隣の席にいても、お隣同士顔を見ないでメールで済ませてしまう。これは関係性の構築を阻んでいることにもなります。便利と思われていたものが、実は不便さを生んでいるのかもしれません。このような些細なことでも改めて感じていただくのも大事なことなのではないでしょうか。
 (サイレンスのアテンドから手話を教わる志村さん)
(サイレンスのアテンドから手話を教わる志村さん)
この先の、未来へ
編集部: これから、日本でどのようなことを伝えていきたいですか?
志村: 特に日本にとって2020年は大きな節目の年になります。「おもてなし」という言葉がずいぶん出ていましたが、英語ができないから来日した外国人に向かい「Welcome to Japan!」なんて言えないよなんて思っている方もいるかもしれない。でも、本当はできなくたっていい。笑顔で「ようこそ」と日本語で伝えられたいいのだと私は思っているのです。言語が違っていても相手は自分を歓迎してくれたんだなって分かりますものね。そのためにもサイレンスってすごくいい経験になると感じています。「今のままでできることはいっぱいあるんだ」ってことを知っていただきたいです。英語ができないとオリンピックの時にボランティアができないとか、手話ができないと聞こえない人と友達になれないということじゃない。英語も手話もできない私が良い見本です。でも、この人と出会った、だからこそもっともっとお話ししたくて手話とか英語を習いたいっていう、そういう風になったら、素敵ですよね。ダークの一般開催が8月末で一旦終わりとなります。次にオープンする時には、できれば2020年までに「ダイアログ・ミュージアム」として、ダークと、サイレンスと、ウィズ・タイムの3つを開催ができる場所がつくれたらと思っています。

志村季世恵(しむら・きよえ)
ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ代表理事、ダイアログ・イン・ザ・ダーク理事、バースセラピスト。心にトラブルを抱える人、子どもや育児に苦しむ人をカウンセリング。その活動を通し『こども環境会議』を設立。1999年からはダイアログ・イン・ザ・ダークの理事となり、多様性への近いと現代社会に対話の必要性を伝えている。
関連サイト:
ダイアログ・イン・サイレンス
※イベントは既に終了しております
関連記事:
「静けさの中の対話」- ダイアログ・イン・サイレンス 日本へ
言葉の飛距離を伸ばす – ダイアログ・イン・サイレンス
注目のキーワード
関連ワード
-
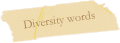
特例子会社Special subsidiary company
障害者の雇用促進・安定を目的に設立される子会社。障害者に特別に配慮するなど一定の条件を満たすことで、特例として親会社に雇用されているものとみなされる。企業側は、障害者雇用率制度で義務づけられている実雇用…詳しく知る
-
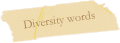
ユニバーサルツーリズムUT
すべての人が楽しめるよう創られた旅行であり、高齢や障がい等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行を目指しているもの(観光庁HPより)。http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisak […]詳しく知る
-
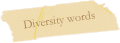
ソーシャルデザインSocial Design
自分の「気づき」や「疑問」を「社会をよくすること」に結びつけ、そのためのアイデアや仕組みをデザインすること。詳しく知る
関連記事
-
16 Jan. 2024
【後編】生きる楽しみを掴む~病と闘う子どもたちに、大人ができること~

- 統合マーケティングプロデューサー
- 中曽根彩華
EVENT, INTERVIEW, NEWS, PROJECT, 医療×ダイバーシティ, こども哲学, アンコンシャス・バイアス, 子育て, 多世代共生, 稀少難病, 子ども, 福祉,
この人の記事
-
18 Nov. 2022
視覚障がいに関わる“壁”を溶かす新規事業とは

- 共同執筆
- ココカラー編集部
EVENT, インクルーシブ・マーケティング, インクルーシブ・デザイン, ユニバーサルデザイン, バリアフリー, CSV, イベント, コミュニケーション, テクノロジー, 障害,