
「がん患者は溺れる者ではない」:がんになった緩和ケア医が語る、人生を泳ぎ切る力

- 副編集長 / プランナー
- 飯沼 瑶子

毎年新たに100万人が、がんになる時代。「がん」経験者、家族、友人、職場の同僚、様々な形で私たちは誰もが「がん」に関わる当事者だ。
「with Cancer:がんを知り、関わりあって、変えていく。」をコンセプトに開催されたWorld Cancer Week 2021のオンラインイベントから【CancerX いのちの対談~がんになった緩和ケア医が語る『残り2年』の生き方・考え方~】のレポートをお届けします。
緩和ケア医が、がんになる
登壇者の関本剛さんは、兵庫県神戸市で訪問医療でのがん患者さんの在宅緩和ケアを行っている医師だ。2001年に医師免許を取得して以来、約10年を消化器内科医として、その後抗がん剤治療の担当医、六甲病院のホスピス勤務を経て、2015年から現在まで関本クリニックで勤務されている。
関本先生のがんが発覚したのは、2019年。当時43歳、ステージ4の肺がんだった。脳への転移があり、根治手術ができないため、延命のための抗がん剤治療を行いながら、医師として業務を続けている。
仕事柄、多くのがん患者さんと関わる関本先生にとっても、自身のがん宣告はもちろん大きな衝撃を伴う出来事だった。
がん発覚は人間ドックでのCT検査がきっかけ。CTの画像に、はっきりと誰が見ても分かる大きさでがんが写っているのを見て、頭が真っ白になった。本当に自分の画像なのか信じられず、思わず名前を確認したという。
その後、精密検査の結果、脳転移も発覚。肺がんは脳に転移しやすいことが知られているが、当時は頭痛などの症状もなかったため、転移しているとは思わなかった。一緒に診断結果を確認した妻と二人「ごめん…」と泣き崩れたという。

ウェビナーの様子。画面左下が関本先生。
生きるためのエンジン
現実を受け止め、治療を開始した関本先生が、仕事を続けることを決意したのは、はじめは経済的な理由からだった。
関本先生には、現在小学4年生と、幼稚園の年長のお子さんがいる。数年以内に死ぬことを自覚し、その後の家族の暮らしを想像した時、自身の治療のために貯金を切り崩すわけにはいかないと思ったという。勤務するクリニックには自分以外にもサポートをお願いできる医師がいることもあり、可能な限り仕事は続けて、自分の治療費と生活費はそこから捻出しようと決めた。
がんの治療はきつい。それでも、前を向いて取り組めるのは子どもの成長を一日でも長く、妻と一緒に見ていたいという気持ちから。家族や大切な人ともっとたくさんの経験をしたい、そのためにも治療費と余暇のための費用をしっかり稼がねば!と思えるからだ。
そして現在、がん発覚から1年以上が経過する中で、担当する患者さんの9割以上が先生自身もがんであることを知っている。それをポジティブに受け止めてくれる方がほとんどだったことは、先生にとって実は予想外だったという。自分の身体や気持ちが持つかわからないが、背に腹は代えられないという覚悟で続けることにした仕事だったが、自分の方が患者さんから元気や生きる勇気をもらうことが多い。仕事は経済的な支えだけではなく、今では精神的な支えにもなっている。「自分にとって、仕事は人生におけるエンジン。」と関本先生は言う。
がん患者さんの中には、ひたすら死の恐怖に圧倒されてしまう人もいる。どうしたらいいか、誰に何を相談すればいいかわからない。病気の痛みに加えて、治療も辛い、なぜさらにこんなに苦しまねばならないのか、何のためにやっているのかという気持ちになるのも当然だ。
溺れる者は藁をもつかむというが、関本先生は「がん患者は溺れる者ではない」と言い切る。
「みんな人生の最後まで、自分で泳ぎ切る力を持っているし、人としてこの世に生まれてきたからには泳ぎ切らなければならない。患者さんに対して、溺れない力をあなたも持っているよと支えるのが緩和ケア医としての自分や標準治療の役割。」
人生を泳ぎ切るには、相当な覚悟が必要だ。そのためにも、ほんの小さなことでも目標や目的を持つことが大切だという。たとえば、次の桜も絶対に見る、来月の子どもの結婚式に出席する、孫が来年生まれる、どんなたわいもないことでもいいので、自分でどんどん見つける必要がある。そのためには医師や家族のサポートも重要だ。
子どもにも病気を共有する
自身の病気について、関本先生はお子さんにもがん発覚初期から開示している。それは病気になる前から、医師として患者さんから相談をもらった際に伝えてきた方針でもあった。
「子どもがたとえ3歳程度でも、言葉が話せてある程度のコミュニケーションが取れる場合には、病気を隠さない方がいい。辛いときには辛いと伝えるべき。同じ屋根の下で暮らしている家族の様子がいつもと違うことは、小さい子どもでも察する。その時に、子どもが蚊帳の外にされていると感じることが良くない。もちろん子どもにとっても親の病気はショッキングなニュースに違いないが、子どもも強いので、周囲のサポートがあればまた立ち上がってくる。理由がわかっている方が、立ち上がりも早い。」
先生のお子さんも、病気で早くに死ぬ可能性があることを伝えた時は驚き、「死なないで」とすがりつくこともあったが、2か月ほど経った頃、上のお子さんから「お父さんが死ぬまでにもう一回温泉に行きたいな」と言われ、「もう一回どころじゃない。何回でも行くわ!」と返して笑いあったという。当時お子さんは小学3年生。2か月で、もう親の病気を受け止めて、そんな思いに至ったことを心強く感じたそうだ。
準備しておくこと
自分がいなくなった後、家族が何か困った時や記念の時のメッセージとして、手紙や映像を残したいと準備を進めているという関本先生。Bucket List=死ぬまでにしたいことをリスト化したものを、イベントの中で共有してくださった。
自分にとっての“ライフレビュー”であり、家族に対しては“生きてきた証”を残すものとして、既に今夏に書籍を出版されたほか、葬儀で妻に喪主の挨拶をしてもらうことが忍びなく、自分で自分の葬儀に来てくださった方への挨拶を動画として準備されたという。
 関本先生のBucket List
関本先生のBucket List
また、定期的な健康診断の重要性についても提起された。
関本先生のがん発覚は人間ドックがきっかけだったが、忙しさを理由に3年ほど定期健康診断を受けていない期間を経ての受診だった。30-40代のがんは進行が速く、毎年健康診断を受けていたとしても治らない場合があるとはいえ、いま健康だから受けても意味がないということは決してない。「特にフリーランスなど、勤務先で受診が必須となっていない人は自分での管理を大切にしてほしい」と語る。
人生の支えになる言葉
いつかは誰もが死を迎える。理屈では分かっていても、死を受け止めることは簡単ではないが、先人の言葉にいつも支えられているという関本先生。
例えば、昨年9月に亡くなった上智大学の教授で司祭でもあるアルフォンス・デーケンさんの言葉。
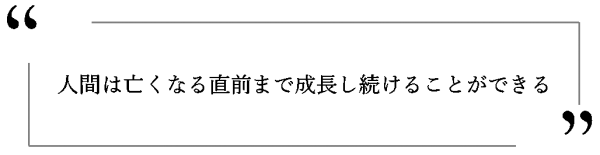
死の恐怖はあるが、こうなったからには仕方がない。その日が来るまで生き抜こう。そうしないと損だなと思えるようになり、生きている限り成長し続けなければと背中を押された。
また、日本のホスピスケアの草分け柏木哲夫医師の言葉。
 今までの生きざまが死にざまにも表れる。たくさんの患者さんのお看取りを手伝ってきた先生にとって、必ずしも肺がんや脳転移があるからといって壮絶な死に方をするわけではないことを事実として経験してきたことも救いになっている。人とのつながりを大切にし、周りへ感謝しながら生きてきた人は、亡くなる時にも家族や医療者に感謝を表しながら穏やかに死んでいく。
今までの生きざまが死にざまにも表れる。たくさんの患者さんのお看取りを手伝ってきた先生にとって、必ずしも肺がんや脳転移があるからといって壮絶な死に方をするわけではないことを事実として経験してきたことも救いになっている。人とのつながりを大切にし、周りへ感謝しながら生きてきた人は、亡くなる時にも家族や医療者に感謝を表しながら穏やかに死んでいく。
関本先生は、残された時間が同年代より短い中でも、濃厚に無駄なく生きていきたいと改めて意識している。
イベントの最後に、関本先生から私たちに送られた言葉を紹介します。
「最善を信じて、最悪に備える。人は誰でも、自分なりの生き抜く力を持っていると思います。ショッキングなことが人生で起こっても、自分を見失わないで。自分の力で強く生きること、そして周りにいる大切な人たちを大事にしてください。それが一番の生きる力になるはずです」
―
■関本先生の著書
「がんになった緩和ケア医が語る「残り2年」の生き方、考え方」

■一般社団法人CancerX
https://cancerx.jp/













