
作りたいのは、みんなが混ぜこぜの世界 – 「True Colors Festival」舞台裏インタビュー(前編)

- 共同執筆
- ココカラー編集部
これまでソーシャルイノベーションにまつわる数々の事業を手掛けてきた「日本財団」。近年ではパラリンピックサポートセンターも設立し、パラスポーツの振興にも携わっています。そんな日本財団が2019年9月から主催しているのが「True Colors Festival – 超ダイバーシティ芸術祭」です。障害・性・世代・言語・国籍などのあらゆる多様性に焦点を当て、ダンス・演劇・ファッション・音楽といった多彩なパフォーミングアーツのイベントを通して、多様性のある社会の重要性を伝えていく芸術祭。その舞台の裏側では、どんな想いを元に企画が進められているのでしょうか。総合プロデューサーである樺沢一朗さんにお話を伺いました。

「True Colors Festival」総合プロデューサー 樺沢一朗さん
なぜ、障害以外のあらゆる多様性にテーマを広げたのか
― 日本財団さんではこれまで、アジア各国で「アジア太平洋障害者芸術祭『True Colours Festival』」を開催し、障害者芸術の支援をされてきました。いよいよ来年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催時期に向けて、日本で2019年9月から「True Colors Festival -超ダイバーシティ芸術祭」を展開されていますが、今回のフェスティバルの特徴を教えて頂けますか。
今回の事業は、我々日本財団がこれまでやってきたこととは異なる特徴が2つあります。一つは取り扱うテーマが「障害」だけでないという点、もう一つは事業のターゲットを一般の人にした点です。
―1つ目の特徴について詳しくお伺いします。今回のフェスティバルで、これまでアジア各国で実施されてきた形式から、「障害」という看板を下ろし、性・世代・国籍といった多様な個性やバックグラウンドを持つ人にまで対象を広げられたのはなぜでしょうか。
日本財団がこれまでおこなってきた事業は、基本的には「障害者に対する支援」というものだったんですね。2018年3月にシンガポールで実施した「True Colours Festival」も、障害者に対して光を当てるという考え方の下でおこなわれたものでした。
ただ、オリパラというのは、日本国内に限って考えると、おそらく何十年に一度くらいの大きなイベントですよね。だからこそ、障害ということだけではない人々の多様性というものを、当事者ではない人・一般の人に伝えるには一番の機会だなと考えました。オリパラのような千載一遇の機会があるのであれば、障害者に対する考え方だけではなくて、もっと広く多様性を考える一番の機会になるな、と。
なので、実施する側のハードルは上がるのですけれども、かなり欲張って、本当に色々な意味での多様性と包括性を追求していこうという形になりました。
― 日本とアジア各国との、障害や多様性に対する課題意識の違いなども、テーマを広げるに至った背景としてあったのでしょうか。
そうですね。東南アジアで実施した事業は、障害の当事者に光を当てることが趣旨としてありました。なぜなら、東南アジアでは障害者は陰の存在だったからです。その人たちをステージに上げて、光の当たる存在になってほしいということがありました。
日本の場合は、そういう状況ではない。施設のバリアフリーもまだまだとはいえ、ある程度は進んでいます。ただ、何より日本が進んでいないのは、「心のバリアフリー」だと思う。障害者に対してどう接したらいいのかが分からないとか、それ以外にも純粋な偏見もまだあるかもしれません。そういう「心の壁」を取り払うのが、今の日本には必要なのではないかと思いました。
また、オリパラという文脈で考えた時も、ハードではなくて、形に見えないソフトのレガシーを残していくことに取り組む方が、今回のオリンピック・パラリンピックの大きなレガシーになるのではないかと思い、当初想定していた規模よりも大幅に拡大して事業を実施していくことに決めました。
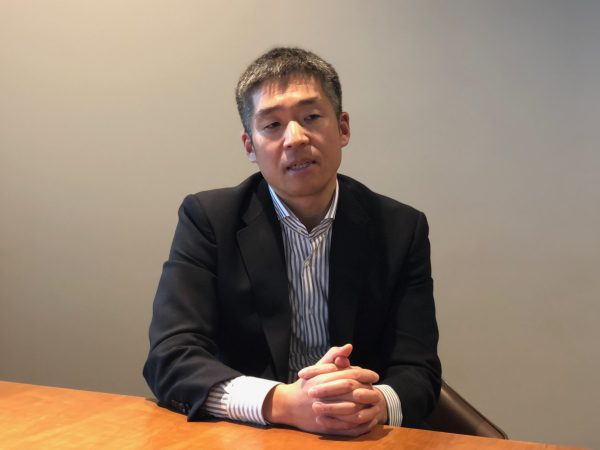
「多様性のある社会」の重要性を伝えるために
― 続いて、フェスティバルのプログラムについてお伺いします。各プログラムの企画をされる際に、こだわられたポイントを教えて頂けますか。
僕が総合プロデューサーという立場で全体を見たときに、芸術的に素晴らしいものを作ってもらうことももちろん大事なのですが、事業の目的は、「『多様性のある社会がいい』というメッセージをより多くの人に伝えていく」という1点ですので、その点を意識して伝え続けています。1つ1つのイベントは、そのメッセージを伝えるための手段です。芸術性が高いものができても、そのメッセージが伝わらないのであれば、意味がないと思っています。
― では、芸術性やエンタテイメント性の担保については、どのように意識されていらっしゃるのでしょうか。
今回の事業は一般の人にターゲットを広げるということなので、より多くの人に伝わるために、より多くの人に興味を持ってもらわないといけないですし、そのためには面白くないといけないので、1つ1つのイベントのエンタテイメント性が担保されているというのは最低条件だと思うんですよね。
ただ、そのエンタテイメント性の追求が、一般の人ではなくて、どうしても意識の高い人に向かっていきがちな部分があります。それだと演じたり作ったりしている方は気持ちがいいのかもしれないが、果たして一般の人にはどう広げられるのか。多様性について普段考えていない人に、どうやって気づきのきっかけを与えられるのか、ということを考える必要があります。
1つのイベントを1つの場所でやるだけではなく、イベント前にはどういう人に告知をしていくのか、イベント後には色々なところにどうやって情報を広めていけるのか。それらをどう掛け算して広がりを作っていけるのか。担当者にはそういうところまで考えて欲しいということを強調して伝えています。
― 今回WEBサイトやSNSアカウントなども充実している印象だったのですが、そのような意図がおありだったのですね。
そうはいっても難しいんですけどね。会場にいて伝わることと、動画やメディアを使って伝わることって全く違うと思うので。でも会場に来られる人の数は限られているので、会場にいることで伝わるものを、どう会場の外まで広げていくかということですね。
― 今回の事業の目的は、「多様性のある社会がいい」というメッセージをより多くの人に伝えていくということですが、なぜ「多様性のある社会」が大事だとお考えなのでしょうか。
「多様性がある社会」と、「個人を認めてくれる社会」は、同じことなんだと思います。ただ、見ている方向が違うだけなんです。自分を中心に考えると、自分がどんな特徴を持った人間であれ、なんとなく世の中が認めてくれる、自分の居場所がある社会というのは、多様性のある、インクルーシブな社会だと思うんですよね。
多様性がある社会というと、マス(社会全体)を見る感じになってしまうんですが、自分に落とし込んで考えると、単純に自分が居心地がいい社会だということです。誰かのためだけではなく、自分にとっても、多様性がある社会って居心地がいいので、それは良くないですか、という話です。
もう一つには、集団としての視点。例えば、ラグビーの日本代表も、日本人だけでチームを構成したらあんなにいい成績は出ないと思うんですよ。色々な人が入っているからこそ、あれだけの強いチームになる。
多様性があるグループ内では違った意見が出ます。でもそれを乗り越えることで圧倒的にクリエーティブなものはそういう集団からの方が生まれると思うんですよね。
多様性がある方が、これからの世の中では強いんじゃないのかな。強いことが必要かどうかというのはありますけれども。これから日本全体のことを考えても、そういう風にしないと、世界の中での居場所がなくなっていくのではないか。そういったことも踏まえると、多様性が認められて、能力を発揮できる社会というのは、個人としても居心地がよく、グループとしても強みを発揮できるんじゃないかなと思うと、全くマイナスの要素がないという気がしています。
― 今回のフェスティバルでは、「ともに力を合わせてつくる」というキーワードを使われているのが印象的なのですが、なぜ企画に「共につくる」要素を取り入れられたのでしょうか。
パフォーミングアーツは、実社会の映し鏡にできると思うからです。フェスティバルがテーマに掲げているダイバーシティというのは、要するに混ぜこぜの状態のことだと思うんですよね。その混ぜこぜの状態が一つの形として化学反応を起こせるのが、パフォーミングアーツだと思っています。
パフォーミングアーツは社会の映し鏡というからには、例えば障害者だけで作ってもそれは非現実的な世界になってしまう。健常者も、障害者も、性的マイノリティの人も、外国人も、子どもも大人もお年寄りも、色々な人がいないといけない。「共につくる」というのはそういう意味です。「共につくる」ことで、同じ属性の人だけでやるものではない面白さや素晴らしさが、伝わるものにできるのではないかと思っています。

10月22日に実施された「True Colors BEAT」のライブパフォーマンス後の様子
芸術がダイバーシティ&インクルージョンの実現に向けてできること
― 芸術やエンタテイメントには、障害者などの社会的マイノリティとされている人々に対して、思わず身構えてしまうような意識を取り払い、観客を含めたみんなを混ぜこぜにする力があると思いますか?
障害のない人が普通の社会で、いわゆる障害があるって言われている人たちを見ると特別な目で見てしまうし、理屈として理解するのが難しいと思うんですよ。パフォーミングアーツは、障害があることが1つの個性になっているのが分かりやすく伝えられる、ということがあると思います。ステージ上で作るパフォーミングアーツは、僕が考えられる限りにおいては、「実社会でいろんな人がいるってことが、ひょっとしたらいいことかもしれない」というのが一番伝わりやすい形なのかなと思いますね。
― これまでの企画で、そのお考えが確信に変わった体験はございましたか。
フェスティバルの最初の企画として9月に実施したブレイクダンスの企画「True Colors Dance」は、それが一番シンプルに伝わりやすいと思いました。
ブレイクダンスって、すごく変な形の動きをするダンスなんですよ。例えば、片手がない人は両手がある人よりも効率的に身体を使えたり、背が小さい人は独楽(こま)みたいにより速く回れたりと、観た時の感じが健常者よりすごいことができるんです。健常者だと長い足が躍る時に邪魔になるケースもあるから、足が短い人はその特徴がダンスをやる上で効率的だったりすることもある。
2024年のパリオリンピックではブレイクダンスが追加競技になる可能性がありますが、ブレイクダンスは同じ基準で採点すれば、障害者と健常者が一緒に戦える競技になるかもと思えるくらい、障害者の障害って言われているところが弱みにならない側面もある、一つの良い例だと思います。

9月10日に渋谷ストリーム前でおこなわれた「True Colors Dance」
Photo:Ryohei Tomita
「True Colors Festival」を通して実現したい社会
―フェスティバルを通して、日本がどのような社会になって欲しいと思われますか。
たぶん、このフェスティバル1つを実施するだけでは変わらないと思うんですよ。オリンピックやパラリンピックなど全てが集まってようやく小さな違いが出てくるかもしれないなというくらい。
こうなって欲しいという日本社会の在り方については、多少なりとも世の中の人が暮らしやすい社会を作っていく上で、ダイバーシティ&インクルージョンについて、すっと理解をしてくれる人の数が増えていること。そういう社会になることで、日本財団がオリパラ後もやっていく事業の効果も大きくなると思います。
― 樺沢様ご自身が、ダイバーシティ&インクルージョンに興味を持たれたり、視点を転換するきっかけになったりした出来事は何だったのでしょうか。
僕は仕事がきっかけです。20数年勤めた会社を辞めて2年前に日本財団に来たんですが、そこで「インクルーシブな社会」という言葉を初めて聞いた。ただ、考え方を聞いた時に抵抗感は全然なかった。20数年間も勤めた会社を辞める人もあんまり居ないわけでして、そういう意味ではやはり日本社会はなかなか柔軟性がない社会でもありますよね。そういうメインストリームから外れた側に自分が置かれた時に、もう少し柔軟性や包容力のある世の中になったほうが、色々な人が生きやすいだろうな、というのは思いました。
ちなみに僕は日本財団に入るまで、インクルーシブな社会というのを想像すらできないほど無知でした。だからこそ、この事業をやる時も、「普通の人」の感覚を自分に置き換えて考えながらやれています。
「普通の人」も、たまたまどこかで接点があると考えが変わるのでしょうね。実際に接点ができるまでは自分ゴトじゃないわけです。だから、どうやって色々な場所にその接点を作り、どうやって色々な人に接点を持ってもらうかが、自分の経験から考えても大事なことなのだと思います。
― 最後に、総合プロデューサーとしてこのフェスティバルにかける想いをお聞かせいただけますでしょうか。
オリンピック・パラリンピックが終わった後に、何を継続的にやっていくのかが一番重要だと思っています。
この1年は、我々日本財団が何十年もやってきたことに対して、集中的に理解が広まる可能性のある特別な1年です。そのためにある種の空中戦のようなことをやっているわけなんですが、そこで終わったら、ただのイベント屋さん・コンサート屋さんになってしまう。日本財団がこの事業をやる強みというのは、今回の事業を世の中の変えるためのものとして、オリパラ後も継続的に取り組んでいけるということだと思っています。
このイベントは、日本財団が何十年も続けてきて、これからまた何十年も続けていくであろう事業・活動の中でも特別なイベントです。オリパラを契機にこのイベントを活用することで、日本財団が目指したいところに効果的にたどり着くことができる。このフェスティバルは、日本財団のビジョンを実現する過程の中間地点にあるものなのです。

― 本日はありがとうございました!
―
樺沢 一朗 氏
日本財団 常務理事
1972年群馬県生まれ。日本財団常務理事。True Colors Festival総合プロデューサー。Wake Forest University卒業(米・ノースカロライナ州)。1996 年5月にNHKに入局。記者として初任地の沖縄以降、東京での勤務の他、バンコク、ワシントンで特派員を務める。2017年7月より現職。元キックボクサーという異色の経歴を持つ。
取材・執筆:鈴木 陽子、細川 萌
注目のキーワード
関連記事
この人の記事
-
18 Nov. 2022
視覚障がいに関わる“壁”を溶かす新規事業とは

- 共同執筆
- ココカラー編集部
EVENT, インクルーシブ・マーケティング, インクルーシブ・デザイン, ユニバーサルデザイン, バリアフリー, CSV, イベント, コミュニケーション, テクノロジー, 障害,













