
「ひとりを起点に、新しいファッションを作る」 「041」FASHION始動【前篇】

- 共同執筆
- ココカラー編集部
多様性の加速する社会においてこれからのあるべきマーケティング手法として、電通ダイバーシティ・ラボが提唱する「インクルーシブ・マーケティング®」。
この度、その先行事例とも言える、ひとりを起点に新しいファッションを作る「O41(オーフォアワン)FASHION」が発表されました。
この取り組みが世に問う新しい価値とは何なのか。そして、何故ファッション業界がその先駆者となったのか。
メディア・クリエーティブ・ソーシャルの力を集結させて社会課題に向き合う「Social WEnnovators(ソーシャル・ウィノベーターズ)澤田智洋さんとユナイテッドアローズ社 上級顧問 クリエイティブディレクション担当の栗野宏文さんの対談からご紹介します。
協力:ユナイテッドアローズ社「ヒトとモノとウツワ」http://taisetsu.united-arrows.co.jp/5302/
前編) 漏れ落ちた「ひとり」のニーズを拾う新たなマーケティングが生まれた
「ひとりのために」から生まれるイノベーション
栗野: 今回のプロジェクトが始まったきっかけは、澤田さんを通じて、洋服を着たくてもさまざまな事情で着られない、けれどもお洒落をしたいという方のために一緒に洋服を作りませんかというお声がけでした。
澤田: 電通、日本テレビ、ジャパンギビング3社の「社会起業家」がそれぞれのリソースを持ち寄り、業界を超えたソーシャルアクションをしようと2016年の秋に立ち上げたSocial WEnnovatorsの企画としてご連絡しました。”I”を”WE”に変えてイノベーションを起こしていこうと。その中で、誰かひとりを起点にプロジェクトをつくる”O41”(ALL FOR ONE)という社会実験を始めたんです。
澤田:私は障害のある友人が大勢いるのですが、彼らがいかに服に対して悩んでいるかを日頃から聞いていたんです、だんだん筋肉が弱くなる障害のある方が、もう着られなくなってもずっとクローゼットの中にユナイテッドアローズ(以下:UA)の服を持っているそうなんですね。ブランド力とかデザインとか好きで。それを所有していることが自分にとって誇りになるのだと。服は、障害のある人にとってはストレスでもあるんだけれど、同時に支えでもある。そういうお話をSocial WEnnovatorsの一員である佐藤大吾さんにしていたら、UAさんとのご縁を頂きました。
栗野: それを伺ってアツくなりました。状況が変わってもやっぱりその服を着たいって思ってくださることって洋服屋冥利につきますね。我々は洋服を世の中に提供すること自体が社会貢献だと思っていますが、今まで自分たちがアクセスできていない人たちにお届けすることができれば、お互いにハッピーですよね。当社の社長もよく、売り手も買い手も社会もみんなよくなる「三方よし」ということを言うのですが、我々にお声がけいただけたことで、自分たちが本質的に大事にしているものに対して何か通じたのかなってすごくそれが嬉しかったし、それをビジネスとして継続性を持ってやることにこそ意味があると思っています。
栗野: 今回の企画を動かすにあたって、分野を横断してオープンに社内募集したら、ある種のドリームチームが結成されました。顧客に車椅子使用の方がいらしてよく話を伺っているという販売チームのメンバーにもオブザーバーみたいに入ってもらって。全然他人事じゃないし、自分たちの持っているスキルがいままでと違う形で活用できるんだったらぜひぜひという感じだったんです。勤務時間で動けるように、会社としてもオーサライズしました。部門を超えて一緒に問題解決することによってお互いの知見がExchange(交換)できるし、これが本当に世に出てくれたら、自分がやったことに対して誇りが持てるし、お金が入ってくること以上に深い喜びが持てるじゃないですか。もともとやりたいと思っていた、組織のリエンジニアリングにも繋がる機会を与えていただいたことを嬉しく思っています。
思わぬ課題と既存のファクターを新たな視点でマッチングする
澤田: プロジェクトの冒頭で、私が所属する一般社団法人障害攻略課も商品開発のサポートで入らせていただき、当事者5名の方の選定、それぞれの服の悩みについて整理をして情報提供させていただきました。
栗野: 澤田さんからいただいた障害のある方の6つの「お悩み」は、実はほとんどが、いわゆる健常者の方の服に対する悩みと同じなんですよ。だから、その問題を解決しようとするアクティビティによって、我々のものづくり自体が進化できるなと感じました。
(6つの悩み)
着脱 サイズ 冷え
素材 フォルム デザイン
澤田: 例えば「冷え」は、サイズとも密接していて、自分にフィットした服がなくてだぼっとしてしまうのでそこから風が入ってしまったり、発達障害のお子さんだと、暴れて服がめくれてしまったり。「素材」だと、たとえば視覚障害のある方が、なめらかなふわっとした服が好きだけれど、気づかないうちに何かにひっかけてもつれてさせてしまうので着られないといった声がありました。
栗野: 冷えにくさや、速乾性、子どもが暴れても平気とかいう視点はこれまでも持っていましたが、自分たちが持っているファクターと知見の使い方が結びついていなかったんです。
澤田: 今回、障害のある「ひとり」の人を起点にしたことで、具体的で明確な課題と、UAが持つ力とを適切にマッチングさせることができたんじゃないかと思うんです。UAの皆様との冒頭のミーティングでお伝えさせていただいたのは、もし可能ならばヒアリングする障害のある方と友達になってくださいと。つまり、トップダウンで「つくってあげる」とかではなく、「友達が悩んでいるから力になろうよ」みたいなフラットな関係をつくってくださいということです。友達にならないと抽出されない悩みって絶対あるじゃないですか。だから、打ち明け合う仲になってほしいなっていう。
栗野:(つくってあげるとかじゃなく)一緒につくる、ですね。
澤田: サンプルがあがるたびに追加ヒアリングしているのでどんどん深化して。個人的に特に好きなのがこの「フレアにもタイトにもなるZIPスカート」です。
栗野: これは画期的ですよ。座りやすいように後ろにボリュームを持たせているんだけれど、そのボリュームが必要ない人は、ちょっとしたアヴァンギャルドなデザインなものとして着ることができる。さらに、プリーツにZIPが付いているので開閉することでフレアスカートにもタイトスカートにもなる。
澤田:画期的ですよね。
栗野: いわゆる健常者の方も全く同じように楽しめるってことが大前提です。じゃないと、僕らがやる意味がない。ファッションってもともと、気持ち補助道具じゃないですか。誰にとっても。そっちとしての認識の方が強いですよね。
インクルーシブなマーケティングが、漏れ落ちたニーズを拾う
澤田: ひとりを深堀りするってすごく大事で。どの企業も何かを開発する時には調査を行うと思うんですけれど、広く浅く定量調査をしてもいわゆる大量生産型のものしか生まれない。一方で定性調査でも、ヒアリングする人が実はそんなにクリティカルなニーズを持っていないとか、似たような属性の人にしか効いてなかったりして発見が狭い。実はそこからこぼれ落ちるニーズってたくさんあるんです。障害のある方って850万人くらいいると言われていて、65歳以上の高齢者3500万を合わせると4300万人。昭和平成型の規格化、標準化という基準から漏れた人口比33%にあたる人たちの、それぞれの中にある「新しい普遍」みたいなのを掘り起こして、そこを起点に服をつくる。ひとりを徹底的に深掘っていくと、実はその周辺にいる同じ課題を持った人にもすごく嬉しい服ができる。これこそが新しいマーケティング活動であり、そこから発見を生むと思っています。。
栗野:もともと洋服屋って、「おあつらえ」で、一人ひとりのニーズに対応していくことからできている。人に会って、話を聞いてものをつくっていたんですね。テーラーさんのように「聞きに行く」という行為自体が今の時代にほとんど失われているのですが、それを社内のデザイナー達が体験できることがすばらしいって思ったんです。障害のある方はよりスペシャルケースだとは思いますけれど根本は一緒ですよね。状況をお伺いして、徹底的に個人に寄り添うことが、ひとつのきっかけになって問題解決の糸口になることが必ずある。それをただテーブル上のプロフェッショナル・スキルとか、デザインという頭のなかだけのコンセプチャルなプロジェクトじゃなくて、もうちょっとフィジカルなデザインみたいなものが形になる。そこが非常にダイナミックなんですよね。
栗野:本来肉体的であるべき洋服屋さんがマスプロダクティブな中でドロップしちゃったものを、もう一回再獲得する、これはすごいことです。いままでと違う例に出会ったことで、自分のもっているスキルとかクリエイティビティの新たな使い方を見出したという…。だから、我々の洋服を提供できて、着ていただけるのも嬉しいけれど、それ以上に関わったスタッフ達の工夫っていうか、頭の使い方における学びの大きさってすごいことであると思うんです。それが、ここまで様々な形で関わってきた全員がいろんなことを学べたなと。
澤田:僕の息子には視覚障害があるんですけど、恥ずかしながら彼が生まれるまで障害のある方とちゃんとコミュニケーションをとったことがなかったんです。どうやって育てたらいいのだろう。恋愛はするのかな。どういう就労するんだろうって情報がゼロだった。だから障害のある当事者の方、ご家族の方、雇用している経営者とかに会い続けていたら、これまでまったく関わってなかった世界の扉をあけてしまったというか。いろんな方がいて、おもしろかったんですね。自分は健常的な価値観に飽きていたんだなって気づいたし、自分が複眼的になる感覚が単純に気持ちよかったので関わり始めたんです。
澤田: そこにはいろんな悩みがあるんですけれど、僕が最初に関わったのがスポーツでした。障害があるからスポーツをしない、スポーツをしないから肥満になって生活習慣病になるという悪循環に陥る。国としても医療費がかさみますし、誰も得してないんですよね。バッドループをグッドループにということで「世界ゆるスポーツ協会」を立ち上げました。たとえば「トントンボイス相撲」というスポーツは、要介護4以上のご高齢の方を起点につくったのですが、「トン」って声をだすと土俵が揺れるんですけれど、発声することで、ご高齢の方は心肺機能の強化になるし、イベントでやるとお子様から20-40代も含めてみんな楽しめます。それは、マスカスタマイゼーションでもなく、超ディープなカスタマイゼーション。大量生産と真逆のアプローチなんです。そこから始めることで、新たな普遍が抽出される。単純にその作業がおもしろかったんです。社会貢献って意識で僕はやってなくって。極論的には自分貢献なんですよね。それが、結果的に社会貢献につながっているなら僕としてもうれしい。
栗野: そもそも社会貢献という言葉が違っていますよね。自分が楽しんでいるのだから。洋服を着たくても着られなかった人が、着られるようになることで一歩踏み出せるとか、そういうことに自分や自分のチームが関われるって、とても嬉しいことじゃないですか。自分が関わる人、出会う人がいい感じにお互いなれるようなことを経験できたら、100億円とかのお金を持つより全然ハッピーだと思います。という風に多くの人が考えるようになると、資本主義社会が抱えている世界の1%に富が集中し、貧富の差が激しすぎて同じテーブルにつけないっていうこととは違う世の中になっていくんじゃないかな?今までと違うハピネスがあるんだっていうことを、もっと見せていきたいなと思っています。
澤田: ひとりを深堀りするってすごく大事で。どの企業も何かを開発する時には調査を行うと思うんですけれど、広く浅く定量調査をしてもいわゆる大量生産型のものしか生まれない。一方で定性調査でも、ヒアリングする人が実はそんなにクリティカルなニーズを持っていないとか、似たような属性の人にしか効いてなかったりして発見が狭い。実はそこからこぼれ落ちるニーズってたくさんあるんです。障害のある方って850万人くらいいると言われていて、65歳以上の高齢者3500万を合わせると4300万人。昭和平成型の規格化、標準化という基準から漏れた人口比33%にあたる人たちの、それぞれの中にある「新しい普遍」みたいなのを掘り起こして、そこを起点に服をつくる。ひとりを徹底的に深掘っていくと、実はその周辺にいる同じ課題を持った人にもすごく嬉しい服ができる。これこそが新しいマーケティング活動であり、そこから発見を生むと思っています。。
栗野:もともと洋服屋って、「おあつらえ」で、一人ひとりのニーズに対応していくことからできている。人に会って、話を聞いてものをつくっていたんですね。テーラーさんのように「聞きに行く」という行為自体が今の時代にほとんど失われているのですが、それを社内のデザイナー達が体験できることがすばらしいって思ったんです。障害のある方はよりスペシャルケースだとは思いますけれど根本は一緒ですよね。状況をお伺いして、徹底的に個人に寄り添うことが、ひとつのきっかけになって問題解決の糸口になることが必ずある。それをただテーブル上のプロフェッショナル・スキルとか、デザインという頭のなかだけのコンセプチャルなプロジェクトじゃなくて、もうちょっとフィジカルなデザインみたいなものが形になる。そこが非常にダイナミックなんですよね。
栗野:本来肉体的であるべき洋服屋さんがマスプロダクティブな中でドロップしちゃったものを、もう一回再獲得する、これはすごいことです。いままでと違う例に出会ったことで、自分のもっているスキルとかクリエイティビティの新たな使い方を見出したという…。だから、我々の洋服を提供できて、着ていただけるのも嬉しいけれど、それ以上に関わったスタッフ達の工夫っていうか、頭の使い方における学びの大きさってすごいことであると思うんです。それが、ここまで様々な形で関わってきた全員がいろんなことを学べたなと。
澤田:僕の息子には視覚障害があるんですけど、恥ずかしながら彼が生まれるまで障害のある方とちゃんとコミュニケーションをとったことがなかったんです。どうやって育てたらいいのだろう。恋愛はするのかな。どういう就労するんだろうって情報がゼロだった。だから障害のある当事者の方、ご家族の方、雇用している経営者とかに会い続けていたら、これまでまったく関わってなかった世界の扉をあけてしまったというか。いろんな方がいて、おもしろかったんですね。自分は健常的な価値観に飽きていたんだなって気づいたし、自分が複眼的になる感覚が単純に気持ちよかったので関わり始めたんです。
澤田: そこにはいろんな悩みがあるんですけれど、僕が最初に関わったのがスポーツでした。障害があるからスポーツをしない、スポーツをしないから肥満になって生活習慣病になるという悪循環に陥る。国としても医療費がかさみますし、誰も得してないんですよね。バッドループをグッドループにということで「世界ゆるスポーツ協会」を立ち上げました。たとえば「トントンボイス相撲」というスポーツは、要介護4のおばあちゃんを起点につくったのですが、「トン」って声をだすと土俵が揺れるんですけれど、発声することで、ご高齢の方は心肺機能の強化になるし、イベントでやるとお子様から20-40代も含めてみんな楽しめます。それは、マスカスタマイゼーションでもなく、超ディープなカスタマイゼーション。大量生産と真逆のアプローチなんです。そこから始めることで、新たな普遍が抽出される。単純にその作業がおもしろかったんです。社会貢献って意識で僕はやってなくって。極論的には自分貢献なんですよね。それが、結果的に社会貢献につながっているなら僕としてもうれしい。
栗野: そもそも社会貢献という言葉が違っていますよね。自分が楽しんでいるのだから。洋服を着たくても着られなかった人が、着られるようになることで一歩踏み出せるとか、そういうことに自分や自分のチームが関われるって、とても嬉しいことじゃないですか。自分が関わる人、出会う人がいい感じにお互いなれるようなことを経験できたら、100億円とかのお金を持つより全然ハッピーだと思います。という風に多くの人が考えるようになると、資本主義社会が抱えている世界の1%に富が集中し、貧富の差が激しすぎて同じテーブルにつけないっていうこととは違う世の中になっていくんじゃないかな?今までと違うハピネスがあるんだっていうことを、もっと見せていきたいなと思っています。
注目のキーワード
関連ワード
-
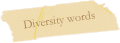
ポテンシャルドライブPotential Drive
これからの働くを考える企業横断プロジェクトチーム「ワークリードプロジェクト」が提唱する、これからの時代にあるべき”働く”を考え、作り上げていくための指針としての概念。 「ひとりひとりが秘めたポテンシャルを最…詳しく知る
-
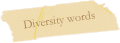
ブロックチェーンBlockchain
インターネットを通じて情報やデータが場所や時間を問わず瞬時に伝達・交換できるのと同様に、金融資産をはじめとするあらゆる「価値」資産の交換が瞬時に実行できるシステム「価値のインターネット」を実現するための…詳しく知る
-
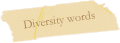
特例子会社Special subsidiary company
障害者の雇用促進・安定を目的に設立される子会社。障害者に特別に配慮するなど一定の条件を満たすことで、特例として親会社に雇用されているものとみなされる。企業側は、障害者雇用率制度で義務づけられている実雇用…詳しく知る
関連記事
この人の記事
-
18 Nov. 2022
視覚障がいに関わる“壁”を溶かす新規事業とは

- 共同執筆
- ココカラー編集部
EVENT, インクルーシブ・マーケティング, インクルーシブ・デザイン, ユニバーサルデザイン, バリアフリー, CSV, イベント, コミュニケーション, テクノロジー, 障害,














