
ボッチャで投じる「地域創生」次の一手~ボッチャ・杉村英孝選手/日本ボッチャ協会代表理事・澤邊芳明氏〜
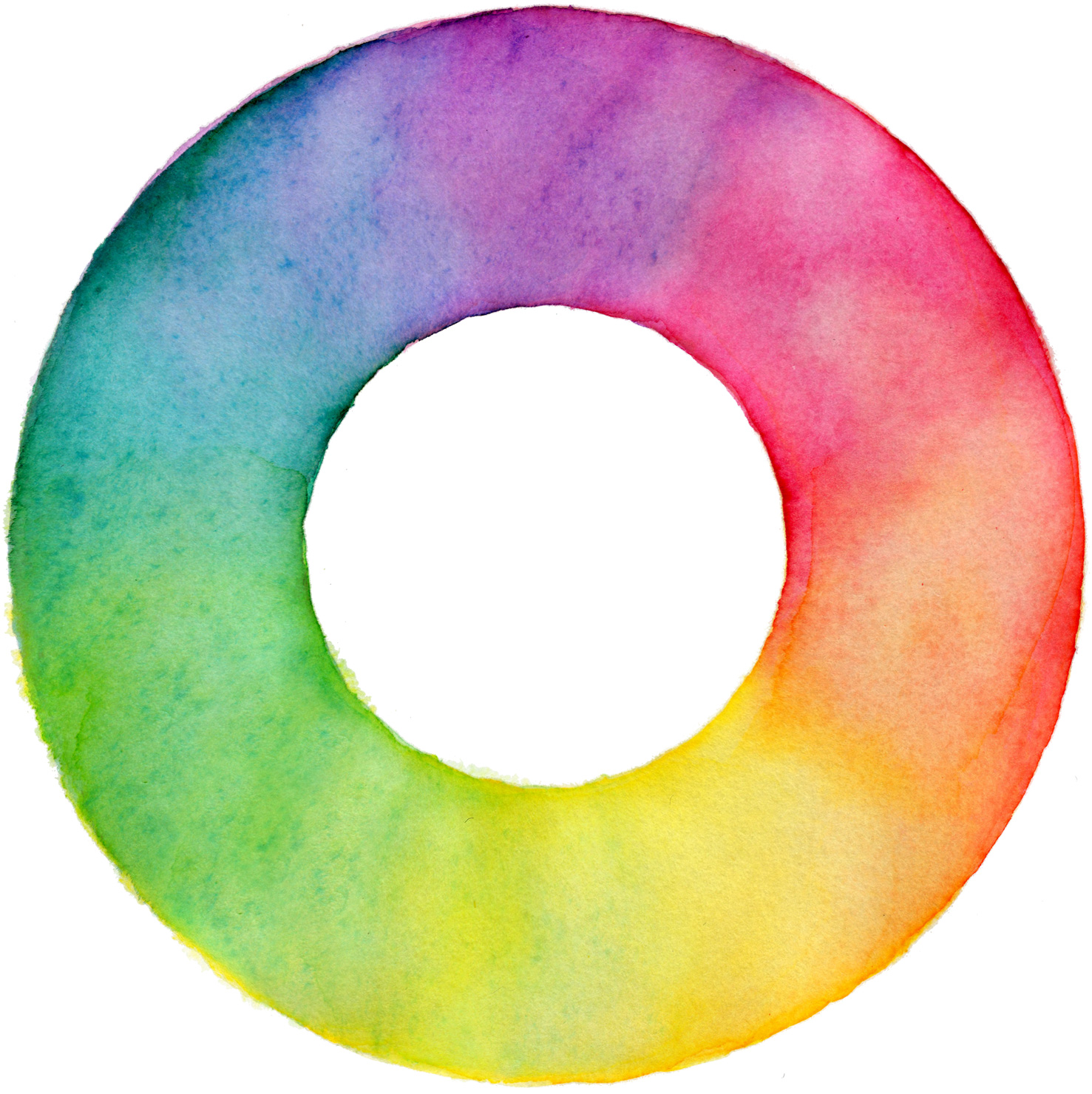
- 共同執筆
- ココカラー編集部
パラアスリートや、パラスポーツを支える人たちに取材し、彼らと一緒に社会を変えるヒントを探るシリーズ「パラスポーツが拓く未来~パラスポーツ連続インタビュー~」。第11回目は、ボッチャ・杉村英孝選手と日本ボッチャ協会代表理事・澤邊芳明氏に聞きました。

杉村英孝選手(左) 澤邊芳明氏(右)
杉村英孝選手(ボッチャ)
静岡県出身/先天性脳性麻痺のため高校まで施設に入りながら、特別支援学校に通う。高校3年生の時、ボッチャと出会い、翌年から本格的に競技をスタート。パラリンピックには、2012年ロンドン大会に初出場。2016年リオデジャネイロ大会では主将を務め、団体戦銀メダルの快挙を遂げた。東京2020大会では、個人戦金メダル、団体戦銅メダルを獲得。伊豆介護センター勤務。
澤邊芳明氏(日本ボッチャ協会代表理事)
2021年5月、日本ボッチャ協会代表理事に就任。18歳の時にバイク事故に遭い、そのリハビリ中、ボッチャに出会う。現在、近未来クリエイティブ集団「1→10(ワントゥーテン)」を率いる。パラスポーツとテクノロジーを組み合わせた「CYBER SPORTSプロジェクト」をはじめ、多くのプロジェクトを手掛ける。
■ボッチャとの「出会い」と、その「魅力」
ボッチャの魅力は「自己選択と自己決定の競技」
杉村:ボッチャと出会ったのは、静岡の障がい者施設に入所していた高校3年生の時。もともとスポーツは好きだったので、学校を卒業してから何かできるものはないかと生活指導の先生に相談し、ボッチャのビデオを見せてもらったのがきっかけです。
ボッチャは、ルールが簡単なので誰でもすぐにできますが、実は緻密な戦略や技術力が必要で、最後の一球まで勝敗がわからないドラマチックな競技です。私が思うボッチャの一番の魅力は、「自己選択と自己決定の競技」であること。介助される日常生活とは違い、試合中は誰の手も借りられない。相手を分析し、どう戦うか。障がいが重くても最終的な判断はすべて選手が行う。これがボッチャの醍醐味であり、大きな魅力だと思います。
私が作った言葉に「百聞は一投にしかず」というのがあります。ボッチャは、実際にボールを投げてみることで、「競技としての楽しさ」や「選手のすごさ」を感じてもらえる競技です。選手にとって、ボッチャは「1㎜を争う頭脳戦」。一投一投の意図を見る側も考えて、自分ならどう投げるかと予想してみる。でも、選手は、その予想をはるかに超えるすごいプレーを見せてくれる。そこが面白いのです。
ボッチャは「言語を超えてコミュニケーションできる競技」
澤邊:私が感じるボッチャの魅力は、3歳ぐらいの子どもから80、90歳のお年寄りまで、ハンデなくできることです。こうした競技は決して多くはなく、あらゆる年代に対して「言語を超えてコミュニケーション」できる競技だと思います。実際やってみると、初めてでも、ボッチャはそこそこできるので、「自分は、うまいかも」と思う。でも、やっていくと、そう簡単には勝てない。「これは奥が深いぞ」と気づくんです。そのあたりが面白いですね。
■東京2020パラリンピックを振り返って
個人としての強化はもちろん、
チームとしての「絆」も強くして臨んだ大会

©フォート・キシモト
杉村:個人としては、リオ大会の悔しい思いから5年間、投球フォームから、車いすや競技用具までをすべて見直し、本当に障がいと体にマッチするものをパーソナルコーチとともに作り上げてきました。それが間違っていなかったことを、「金メダル」という形で証明できたのがうれしかったですね。
東京2020大会へ向けてのチームづくりでは、コロナ禍で強化合宿ができず、本当につらい時期もありました。とにかく、「健康第一」を全員で徹底。そして、オンラインミーティングをやって、みんなでアイデアを出し合いながら活動に取り組みました。家で競技感覚を磨くために「テーブルボッチャ」を始めたり、選手やスタッフ、コーチに向けて、誕生日の「おめでとう動画」を作ってお祝いしたり。そうした積み重ねで築いた一体感が、「日本チームの強さ」になったと思います。
パラリンピックの開会式は、試合を控えていて参加できませんでしたが、「開会式はテレビでみんなで!」という声が自然に上がり、そうした光景からもチームとしての「成長と絆」を感じました。聖火の最終点火者の一人として合宿で一緒だったボッチャの選手が登場すると、みんなで手を振ったりしてすごく盛り上がりました。
パラリンピックは、自分の可能性を追求させてくれる場
杉村:東京2020大会では、絶対的なチャレンジャーとして過去の自分に打ち克つことと、大好きなボッチャを大舞台で楽しむことをテーマに臨みました。そして、驚くほど「平常心」で試合ができ、本当に毎試合が楽しかったですね。パラリンピックは、選手にとっては夢の舞台。でも、そこへの道のりは険しく、そういう意味で自分の可能性を追求させてくれる場であると感じました。
澤邊:今回、コロナ禍での東京2020大会開催については賛否両論でしたが、それでもパラリンピックは、社会に受け入れられているように感じました。その理由は、パラリンピックの持つ「共生社会」や「人間の可能性」といったテーマ、つまり「スポーツを超えたいろいろな気づき」があることに、共感してもらえたからではないかと思います。
■さまざまな普及活動による変化の手応え
ボッチャの認知度は確実に高まっている

©フォート・キシモト
杉村:ボッチャの普及活動としては、日本ボッチャ協会主催の「ボッチャキャラバン」や「東京カップ」があり、ここ数年で地域の方々と触れ合う機会がとても増えました。特に「東京カップ」は、障がい者と健常者が真剣勝負できる大会として、すごく盛り上がりを見せています。
澤邊:実際、日本ボッチャ協会の調査によると、ボッチャの認知度は2014年に2%ぐらいだったのが、2019年は40%ぐらい。私の感覚では、いまは50%を超えているかなと。協会の方にも「ボッチャをやりたい」という声がたくさん来ていて、東京2020大会後は「私も選手になりたい」という声がすごく増えているのがうれしいです。さらに、2021年流行語大賞トップ10に杉村さんの得意技「スギムライジング」が入るなど、ボッチャに対する認識のフェーズが変わった気がします。
障がい者に対する意識や理解も、東京2020大会開催が決まってからの6~7年でだいぶ進んだと感じます。義足の選手が出ている試合を見ても、「アスリート」としての活躍に感動してもらい、競技を楽しめるなど、健常者、障がい者といったハードルは、確実に下がってきていると思います。
東京2020大会で生まれたムーブメントを、終わらせてはいけない
杉村:今回、テレビやSNSを通じて、多くの人がボッチャに興味・関心を持ってくださいました。次の一歩は、そうした方々を実際に体験する機会にまでつなげていくことです。このムーブメントをここで終わらせてはいけない。だから、選手それぞれが、自分のできることを考えて取り組んでいくことですね。
澤邊:協会側としては、「ボッチャを見てください」ではなく、「どう面白く見てもらえるようにするか」を考えた普及活動をやらないといけない。東京2020大会という枠組みがなくなったいま、ここからが勝負どころだと思います。
■ボッチャ選手へのサポート、今後の課題
競技の部分だけでなく、選手のライフスタイルを理解したサポートを

©フォート・キシモト
杉村:やはりパラアスリートの活動強化には、経済的な負担や練習環境の確保への下支えがないとなかなか踏み込めないのが現実です。私自身、東京2020大会では「専任コーチ制度」のおかげで、パーソナルコーチをつけてもらい、このサポートが成果につながったと思っています。
ボッチャの選手は、アスリートである一方「重度障がい者」です。移動や食事、トイレなどのサポートが必要となります。競技の部分だけでなく、選手のライフスタイルを理解したうえでのサポート体制ができたらうれしいですね。
私の場合は、地元の高齢者介護の企業に勤めていて、その代表が私の後援会の会長でもあり、仕事だけでなく競技活動のことも理解してくれた上でサポートしていただいています。高齢者施設なので、バリアフリーなどのハード面では問題ありませんし、たまに利用者さんとボッチャをしたりもします。私が入社した時から、少しずつ成長していく姿を見てもらえて、本当によかったなと思っています。
■ボッチャに期待される可能性
地域とのつながりを大切にして
地域からボッチャの広がりをつくっていきたい
杉村:私の地元の伊東市は、東京2020大会に向けて市を挙げて応援してくれました。いま街中を歩くと、よく「ボッチャの杉村選手ですよね」と声をかけてもらえ、たくさんの人が東京2020大会を見てくれたと実感しています。実は大会前に、私の後援会の主催で「伊東温泉ボッチャ大会」を開催しました。親子での参加もあり、小さいお子さんたちがボッチャを楽しむ姿を見て、地元の方がボッチャに触れる機会づくりにもっと取り組みたいという想いが強くなりました。
澤邊:これからのボッチャの広がりを考えた時、たとえば「ボッチャバー」とか「ボッチャカフェ」をやりたいという相談もあって、いろいろなボッチャの楽しみ方があっていいのではと思っています。また、京都ボッチャ協会では、4チームが同時に投げる「スクエアボッチャ」という新しい楽しみ方を開発して、地域を盛り上げています。「地域創生」という点でも、ボッチャは有効なツールになりそうです。先ほどの温泉ボッチャ大会でも、ジャックボール(目標球)を温泉卵のデザインにしたり(笑)、「地域性を加えたアイデア」をどんどん付加できると面白いですね。
スポーツの世界では全体的にエンタメ化が進んでいますし、ボッチャやパラスポーツが、スポーツ×地域創生の新しい可能性を拓くのではないでしょうか。
―――――――
いまやメディアに引っ張りだこの杉村選手ですが、澤邉さんとの掛け合いでは新たな一面を見せてくれました。まわりの人々との絆を何より大切にする杉村選手ならではのボッチャ観、社会観が、パラスポーツの新たな可能性を拓いてくれそうです。
《参考情報》
・ボッチャの選手、大会等の情報
ボッチャ1万人プロジェクト公式Instagram
https://www.instagram.com/oneproject.boccia/?ref=badge
・過去の試合動画はこちら
第23回日本ボッチャ選手権大会
1日目:https://www.youtube.com/watch?v=j67_KuRZbwU
2日目:https://www.youtube.com/watch?v=B0fPf8QTuK4
取材・執筆:桑原寿、吉永惠一、斉藤浩一
編集:濱崎伸洋
注目のキーワード
関連ワード
-
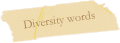
特例子会社Special subsidiary company
障害者の雇用促進・安定を目的に設立される子会社。障害者に特別に配慮するなど一定の条件を満たすことで、特例として親会社に雇用されているものとみなされる。企業側は、障害者雇用率制度で義務づけられている実雇用…詳しく知る
-
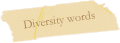
ユニバーサルツーリズムUT
すべての人が楽しめるよう創られた旅行であり、高齢や障がい等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行を目指しているもの(観光庁HPより)。http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisak […]詳しく知る
関連記事
-
13 Sep. 2024
DEIな企業風土の耕し方 vol.2パナソニック コネクトの場合(後編)

- 副編集長 / Business Designer
- 硲祥子
INTERVIEW, PROJECT, 働き方の多様性, ダイバーシティキャリア, 企業,
-
25 Jul. 2024
新連載! DEIな企業風土の耕し方 vol.1 アマゾンジャパンの場合(後編)

- 副編集長 / Business Designer
- 硲祥子
INTERVIEW, PROJECT, 働き方の多様性, インクルージョン, LGBT, ジェンダー, ダイバーシティキャリア, 企業,
この人の記事
-
18 Nov. 2022
視覚障がいに関わる“壁”を溶かす新規事業とは
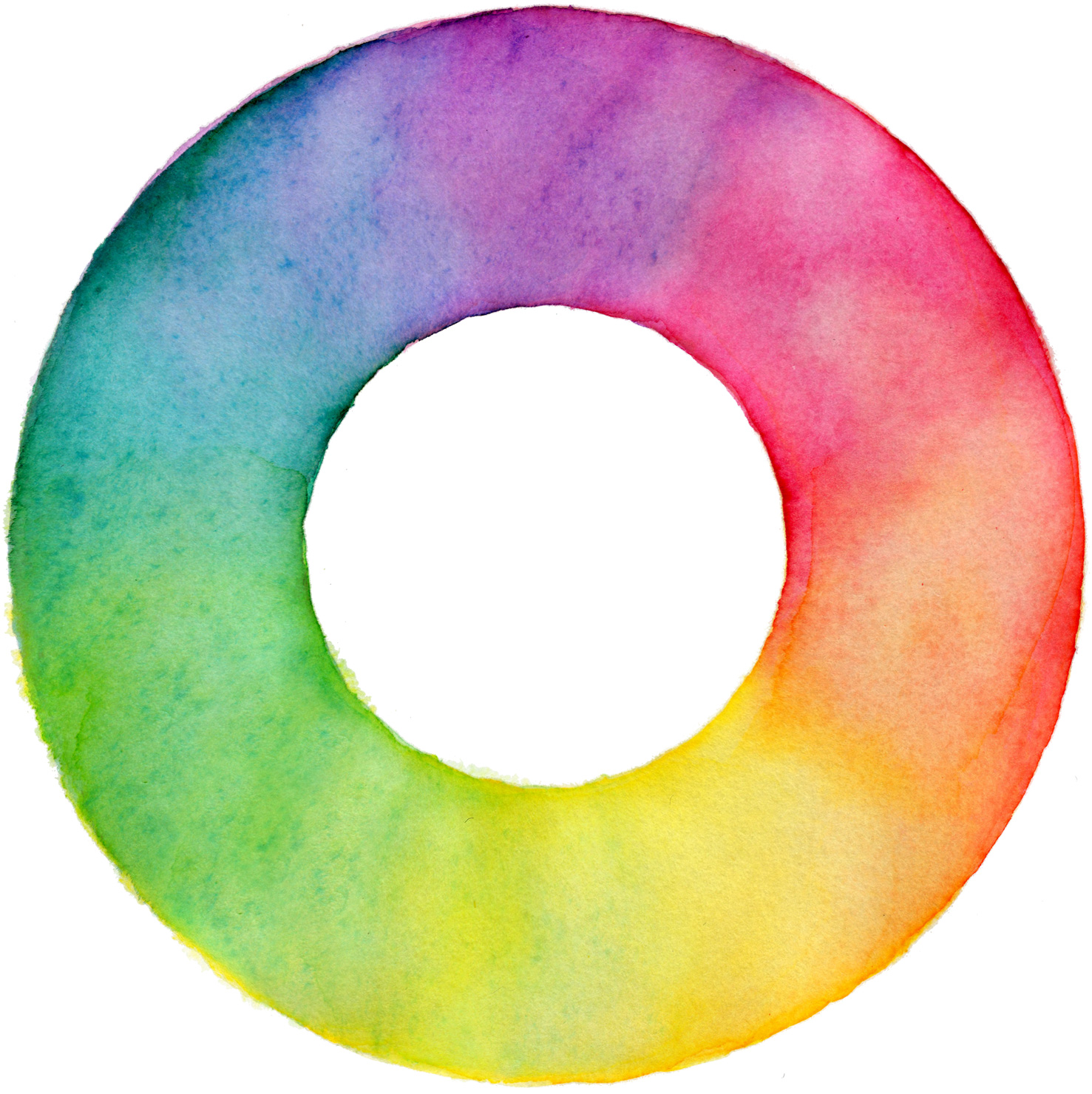
- 共同執筆
- ココカラー編集部
EVENT, インクルーシブ・マーケティング, インクルーシブ・デザイン, ユニバーサルデザイン, バリアフリー, CSV, イベント, コミュニケーション, テクノロジー, 障害,









