
ブラインドサッカー世界選手権 Vol.3 その先の、社会変革へ

- cococolor事業部長 / cococolor発行人
- 林孝裕
アジア初の世界選手権を国立代々木競技場フットサルコートで開催し、見事に成功に結びつけた、日本ブラインドサッカー協会。大会のキャッチコピーを書いたコピーライターの澤田さんと協会を訪れ、事務局長の松崎さんと、今大会を振り返り、今後の展望について語りあいました。
(聞き手:cococolor編集部 林)
世界の観客を沸き立たせた、感動の9日間
(左から:コピーライター澤田氏、編集部林、日本ブラインドサッカー協会早川氏、松崎氏)
編集部(林)/澤田(以下敬称略):
世界選手権の成功、おめでとうございます!
松崎:
ありがとうございます。お陰さまでチケットを購入して来場してくれた人たちが約6300人、招待も含めると約8000人の動員がありました。障がい者スポーツで、有料でそれほど多くの人たちが訪れる場と雰囲気を、2020年のパラリンピック開催の6年前にあたるこの時期に実現できたことは、僕たちにとっても、とても大きな成果だったと感じています。
実際にご覧になって、どんなことを感じましたか?
編集部(林):
原宿駅から会場に向かって歩いていく際に「ニッポン、ニッポン」というエールが次第に大きくなっていくのを耳にして、すごい瞬間に立ち会っていると身震いしました。世界の強豪と日本代表がぶつかり合う迫力に圧倒されましたし、観戦に慣れていない人たちが、(静かに観戦するというルールを忘れ)思わず声を出してしまうような緊迫感も含め、独特の一体感や熱気を感じました。
澤田:
ツイッターでも、ブラサカという言葉を発信する人たちが日に日に増えてきて。ブラインドサッカーに初めて出会う人たちの間にも感動が広がっているのを実感し、改めて、破壊力のあるコンテンツだなと思いました。
編集部(林):
これだけの盛り上がりに対し、選手の反応はいかがでしたか?
松崎:
正直、驚いていたと思います。満員の客席から応援されるというあの空気感は、体験してみないとわからない。私たちも「一体感のある会場とは、こういう力を持っているのか」と改めて実感しました。サポーターやファンから必死に応援されて、必死にサッカーをする。あの一体感がつくりあげられたということに、意義があったと思います。
編集部(林):
ある意味、選手にとっても、ブラインドサッカーの新しい可能性を感じた場だったと言えますね。
松崎:
観客のみなさんが、音を出すことを気にしてくださっていましたが、選手たちは、実は意外と気にしていないんです。ものすごい集中力の中でやっているので。逆に、自分たちのプレーに、観客席から思わず歓声が上がるというシチュエーション自体に感動していたと思います。観客が湧いて「シーッ」と制されるというシチュエーションはこれまで海外遠征時に相手チームに対してしか体験したことがなく、そういうムードに包まれることにみんな憧れていたんです。それが、今回実際に体験できましたから。ある意味、ブラインドサッカーというスポーツは、こういうものだったのか!と、選手も私たちも改めて知ったと言えるでしょうね。
初めての挑戦、乗り越えていった壁
松崎:
実際には、開幕戦のチケットが完売したのは2-3日前とギリギリ。お客さんが全然入らない悪夢にうなされたり、集客のプレッシャーに随分苦しめられました。
都心でこういった大会を初めて開催するにあたり、手続きや許認可を含めたさまざまな壁にもぶち当たりました。それをひとつひとつクリアしていけたのは「僕らがやらなかったら誰がやるんだ」という、気合と根性だけかもしれません。ブラインドサッカーが世界選手権を実施するのに消極的な施策は今後のパラリンピックムーブメントに影響するとも考えていました。
全スタッフが意義とビジョンを共有していた。だからこそ難しいことを実現することができたんだと思います。チケットだって、無料にした方が事業上のメリットは大きいんです。けれども、障がい者スポーツで有料チケットを設定しても、これだけ人が集まるんだということを、自分たちは証明したかった。今回の大会で、自分たちがつまづいたこと、乗り越えたことが、他の競技スポーツの方々の踏み台になっていくことが大事だと考えてきました。
ちょうど世界選手権が終わったタイミングで、NHKのニュースで、「パラリンピックへの関心が低い」ということが報道されましたが、もしも自分たちが、そこそこレベルの、パッとしない世界選手権しか開催できていなかったら、あのニュースのあとで、みなさんに「やっぱり、そんなものだよね・・・」と思われてしまったのかもしれないなと、考えさせられましたね。
澤田:
集客は、メディアの影響が大きかったのでしょうか?
松崎:
メディア報道をきっかけに来た人たちもいましたが、サポーターの方々や、これまでに企業研修やスポ育などの企画でブラサカといい出会いをしてきた人たちが支えてくれたところが大きかったと思います。これまで、私たちがさまざまな事業活動を通じて、超長期的マーケティングを続けていった成果とも言えるかもしれません。日本が初戦に勝利したことが、その後のよい雰囲気の維持につながったところも大きいと思います。
編集部(林):日本での開催について、海外からの評価はいかがでしたか?
松崎:一言でいえば、大絶賛でした。「日本すごい!」と。運営面、雰囲気ともに、とても評価が高かったです。閉会式では、日本人のサポーターが参加国すべての国旗を持って応援してくれたシーンもあり、国際組織のチェアマンからも賞賛いただきました。競技先進国でも閉会式にあれだけのサポーターが残ってくれるというのはあまりないことだと思います。大会の動画配信も、アルゼンチンから3000、フランスから2000ほどのビューがカウントされ、ブラインドサッカーが世界中で観られるスポーツであることを改めて実感しました。
それらの実績から、IBSA(国際視覚障がい者スポーツ連盟)への「日本にマーケティングとファンドレイジングを担当させて欲しい」というアピールにも、徐々に耳を傾けてもらえるようになったんですよ。
編集部(林):
「アジア初開催」を超えて、世界に対して意義を打ち出せたとも言えますね。
松崎:
この大会でのスタンダードが、今後の大会での、ひとつの参考基準となっていけばなと思っています。
障がい者スポーツとしての意義
松崎:
世界選手権は、世界ナンバーワンを決めるために、人生をかけた選手たちが集まる大会です。彼らのプレー自体が持っている魅力、プレーの技術の高さ、そこに至るまでの努力には相当のものがあります。ブラジル、アルゼンチンといったチームは他国と比べ別格と言えますが、彼らも最初からあそこまでできていたわけじゃないし、そもそも「見えない」というところに、ものがたりがある。そういったところも、ブラインドサッカー世界選手権の醍醐味のひとつですね。
編集部(林):
観戦していると、選手ひとりひとりの人柄やキャラクターが伝わってきます。そしてその選手たちをハブにまさに会場が一体になっていく感覚がある。その時に、障がい者という存在は全く別の価値を持つようになっていることに後になって気が付く瞬間があるんですね。障がい者スポーツ、そしてスポーツというもののいろいろな側面が見えてきますね。
(試合後サポーターの鳴り止まぬ歓声にこたえる姿は、ヒーロー以外の何ものでもない)
松崎:
僕は、ブラインドサッカーをスポーツとしてみせていくことが大事であると同時に、障がい者スポーツとしての意義を伝えていくことも重要だと思っています。よく、報道などで「”脱”障がい者スポーツを目指そう」とか「障がい者スポーツであることで下駄をはかせているのではないか」という声も耳にしますが、彼らが、社会的に「マイナス」を踏まえて挑戦していることは、すごく大事なことだと思うんです。だから、スポーツとして注目されることが大事であると同時に、社会的な見られ方もして欲しい。その両方なんです。
澤田:
選手には、複雑な過去があると同時に、今スポーツができる喜びがある。だからこそ、全力で楽しみ、うまくなろうと頑張っている、その感謝と覚悟を兼ね備えた姿勢に、人としてとても魅力を感じます。
松崎:
そうですね。選手に聞くと、自分のためというより、誰かのためにやっていると答える人が圧倒的に多いと思うんですよね。代表選手に自分のためだけにやっているという人はおそらく一人もいないんじゃないかと思います。それだけの想いを持ってみんなプレーをしているんです。
進化する強さ
編集部(林):
日本ブラインドサッカー協会の皆さんは、「ブラインドサッカーを通じて、視覚障がい者と健常者が当たり前に混ざり合う社会を実現すること」というビジョンを掲げています。これについて、世界選手権後、選手のみなさんとは何か話し合いましたか?
松崎:
ビジョンへの理解にはいまは安定感があるので、そこはあまり語っていません。今はむしろ、ビジョンを実現するために、強い代表になるためにどうするべきかを詰める時だと思っています。世界選手権での6位入賞は評価いただいてますが、目標に掲げていた4位からはビハインドなのは間違いない。僕らとしても、世界選手権で注目を集めている時にもっと今後の代表について発信すべきだったなど、反省点も多々ありました。
澤田:
障がい者スポーツ自体が、そんなに歴史も長くなく、完成されているわけではない。つまり、スポーツそのものも、運営する側も進化していく、その伸びしろが面白いところだと思います。日本のように、なにもかもが成熟し形骸化していくような社会で、自分たちも一体となり、つくっていくという高揚感が味わえる。こういうグルーブ、いきものみたいな感覚が、ずっと続いていって欲しいなと・・・。
松崎:
本来、不慮な事故による障害は、なくなった方がいいわけですよね。先進国多くの国ではその数は減っているけれど、途上国ではまだ増えている。そして世界の視覚障がい者の6割は、日本の医療技術があれば治せると言われているそうです。障がい者を含む多様性ある社会をつくることと、障害自体を減らしていくことと。パラドクスのようですが、その両方を考えていくことが必要だなと。
(「見えない。そんだけ。」とキャッチの添えられた世界選手権2014のポスター)
澤田:
僕は、障がい者はメタファだと思っているんです。今回、「見えない。そんだけ。」というコピーを書かせていただいたのですが、それも、「障害」を、メタファとして感じて欲しいと思ったからで。経営者は偉くて、雇われている人は偉くない、みたいな、そういう決めつけが、社会のあちこちに散りばめられていると思うのですが、「そんだけ。」というメッセージを打ち出したのは、そういう前提を、破壊したかったからなんです。みんな大したことないし、みんなすごいというか。障がい者は大変だし、重く悲しく受け止められるけれど、選手としては飄々としている。障がい者って別に重くない。楽しい人は楽しく、後ろ向きな人は後ろ向き。みんなと同じだよと。監視社会が過剰化した世界では、ちょっとしたミスでも、ダメだと決めつけられてしまう。けれどもそれは、そのひとの一部分でしかない。そうじゃなくて「そんだけ。」(So What?)と言い切って生きていいんじゃないかって思うんですよ。「そんだけ。」には、すべての良し悪しを軽やかにフラットにしてしまうようなメタメッセージがある気がしますし、そういうメッセージ性を、選手はプレーで証明する。彼ら自身がメッセージ機能を持っている。
松崎:
それが、パラリンピックアスリートの役割なのでしょうね。
澤田:
障がいを持った人たちに触れることで、僕ら自身も元気をもらいます。例えば、小学校のクラスの中に、みんなが支えあおうとする雰囲気が生まれるといった話を耳にします。日本ブラインドサッカー協会は、日本中に「障がい」というものを浸透させ、出会った人が、もっとがんばらなきゃと感じたり、やさしさみたいのを思い出したりすることによって、マインドセットを変えていく。そういう役割を果たしているのかなと感じるんです。
松崎:
それは、僕らの概念でいうと、多様性なんですね。ひとりひとりを際立たせている、すべての違い。ダイバーシティ社会とは、ひとりひとりの違いを活かし合っていくところだと、僕らは考えているんです。障がい者スポーツを通じて、そういうきっかけにつながるものを、社会に振りまいていけたらと思っています。
人が変わる、社会が変化する
松崎:
社会を変えていくには、社会の中枢にいる影響力がある方のマインドが変わることの影響がめちゃくちゃ大きいと思うんです。パラリンピックはそういうきっかけになるわけですが、今回、行政関係者の皆さんが大勢観戦し、あの雰囲気を感じてくれたことが本当に大きかったと思います。視察に来たみなさんも「こういう雰囲気なんですね。こう変わればいいんですね。でもこれは当たり前にできることじゃないんですね」と感じ取ってくれた。これから2020年のパラリンピックをどうしようか考えていく人たちが、あの場に一緒にいてくれたことが、これから社会を考えていく上で、とても重要だったと思います。
澤田:
テレビや記事からの情報は、目で感じるだけの、いわば「目感」。会場にきて、全身で感じないと、伝わらないですよね。今回、世界選手権でそれを「体感」した人たちの心には、その財産がずっと残っていくだろうなと感じます。
松崎:
オリンピック・パラリンピックに関係する皆さんや障がい者スポーツに関係する方々からも、この選手権を見て、我々にももっとできることがあるはずと、言葉をいただきました。これまで少しずつ積み重ねてきた活動があったからこそ、こういう思いを共有できたのだろうと思っています。
編集部(林):
世界選手権が終わり、今の気持ちは?
松崎:
選手も含めて、あまり余韻にひたっている感覚はなく、まだまだ、僕らの掲げるビジョンの達成に向けた通過点にすぎないと感じていると思います。今年はそのベンチマークイヤーでしたが、これを次の競技大会や事業活動にどう結びつけていくかがチャレンジですね。
澤田:
ビジョン実現のためにひたすら突き進む。まさにベンチャー精神ですよね。
松崎:
ベンチャーであると同時に、僕らは社会変革アクターでありたいと思っているんです。社会を変革するには、ひとつひとつの立ちはだかる障害を越えていかなくてはならないんですね。できない理由はいくらでも見つかる。でも、そこから逃げずに乗り越えた先に、ビジョンへの道筋ができると僕らは思っているし、僕らが提供しているチームビルティングのワークショップやスポ育で伝えているのも、まさにそういうことなんです。
編集部(林):
ひとりひとりのスタッフにビジョンが共有されているから、そういう思い切った行動がとれるのかもしれませんね。
松崎:
まさにビジョンだと思いますね。ビジョンが明記され、浸透しているから、言動のズレに気づくことができる。「それはおかしくない?」とスタッフから僕自身が突き上げられることも多々ありますが(笑)。
編集部(林):
これから先、どのようなステップを考えていますか。
松崎:
ビジョン実現にドライブをかけるファクターは、日本代表なんです。代表という神輿が大きく輝いていると、それを担ぐ人が集まってくる。選手強化のサイクルは、大事な要因になっていくと思います。スポーツにとって勝ち負けは醍醐味でもあるし、僕らを熱狂させます。ブラインドサッカーというスポーツそのものが、社会変革を大きくドライブしていく。それが、パラリンピックのような大装置が世界を変えることにつながる理由でもあると思うのです。
>取材を終えて
常に明確なビジョンのもとに、高いハードルを自らに与え、様々な困難を乗り越えた末の、今回の世界選手権の成果。それは障がい者スポーツという枠を越えて、スポーツを越えて、障害を越えて、多くの人々がそれぞれの視点で、今まで知らなかった新しい何かを感じ、考えるきっかけをつくったのではないかと思います。
2020年というわかりやすいタイミングがある中で、それをどのように活かしていくことができるのか。それまでの日々、そしてそこから先の日々をどのように描いていくべきなのか。この数日間の出来事を体感し、何かを感じた一人ひとりが、考え続け、行動していくことが必要なのだと思います。
日本ブラインドサッカー協会
事務局長 松崎 英吾さん
日本ブラインドサッカー協会事務局長。慶応義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所研究員。国際基督教大学卒。1979年生まれ/2児の父。
学 生時代に、偶然に出会ったブラインドサッカーに衝撃を受け、深く関わるようになる。大学卒業後は、㈱ダイヤモンド社に勤務。一般企業での業務の傍らブライ ンドサッカーの手伝いを続けていたが、「ブラインドサッカーを通じて社会を変えたい」との想いで、日本視覚障がい者サッカー協会(現・日本ブラインドサッ カー協会)の事務局長に就任。「サッカーで混ざる」をビジョンに掲げる。スポーツに関わる障がい者が社会で力を発揮できていない現状に疑問を抱き、障がい 者雇用についても啓発を続ける。サステナビリティをもった障がい者スポーツ組織の経営を目指し、事業型非営利スポーツ組織を目指す。
コピーライター 澤田 智洋さん
企業、地方、人、スポーツ等、あらゆるもののコピーを手がける。その他「未来のふつうのスポーツ」をテーマに、誰も排除しないスポーツ事業を進めている。日本バブルサッカー協会理事長。
参考:
ISBAブラインドサッカー世界選手権2014
日本ブラインドサッカー協会
関連記事:
ブラインドサッカー世界選手権Vol.1 新しい世界へのキックオフ!
ブラインドサッカー世界選手権Vol.2 代々木で起きた熱狂
注目のキーワード
関連ワード
-
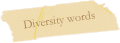
特例子会社Special subsidiary company
障害者の雇用促進・安定を目的に設立される子会社。障害者に特別に配慮するなど一定の条件を満たすことで、特例として親会社に雇用されているものとみなされる。企業側は、障害者雇用率制度で義務づけられている実雇用…詳しく知る
-
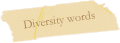
ユニバーサルツーリズムUT
すべての人が楽しめるよう創られた旅行であり、高齢や障がい等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行を目指しているもの(観光庁HPより)。http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisak […]詳しく知る
関連記事
この人の記事
-
23 Jul. 2020
WASEDA NEOダイバーシティシリーズ「インクルーシブ・マーケティング」

- cococolor事業部長 / cococolor発行人
- 林孝裕
EVENT, PROJECT, インクルーシブ・マーケティング, インクルーシブ・デザイン, インクルージョン, 企業, 大学,




















